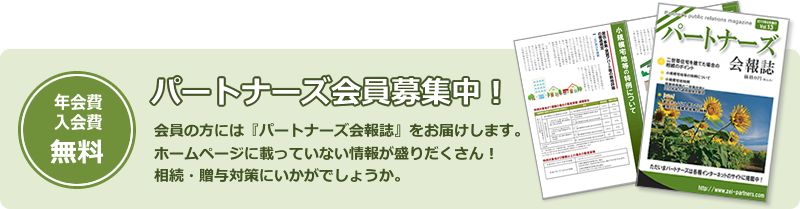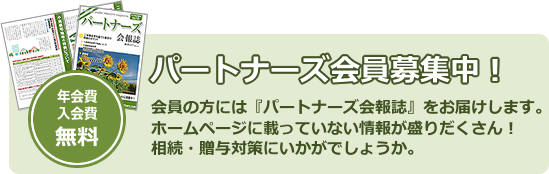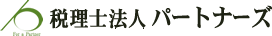遺言のルールについて

今回のコラムは“遺言”についての決まりごとをお伝えします。
遺言とは、亡くなった人が生前に、自分の持っていた財産の処分方法を示し、死後に遺言通りに実行する制度です。
遺言は、亡くなった人の意思であり、唯一、遺族に意思を伝えることができる方法です。
しかし、内容の真意は本人に確かめることはできません。そのため、亡くなった人の意思を保証するために、民法では厳格なルールを定め、決められた手続に従って遺言書の作成を要求しています。民法で定める方式に従わなければ、遺言は無効になります。その他、遺言が無効になる場合を下記に記していきます。
遺言が無効になる場合とは
① 15歳未満の人や、意思能力のない人の遺言
② 遺言者が他人と意思の疎通ができない状態、または遺言した内容を本人が理解できない状態で作成された遺言書
③ 2人以上の遺言者が、同一の証書に記載しているとき
※ご夫婦の共同名義の財産が多くても、遺言書をひとつで済ませることはできません。各自の遺言書を作成する必要があります。
検認
検認とは、遺言書を家庭裁判所で内容を確認し、相続人全員に公表することです。
遺言は、遺言者が死亡した時から効力が発生します。同時に、遺言者の死亡は相続の開始でもあります。そのため、遺言の内容を相続人全員が知る必要があります。ただし、相続人を全員集め、勝手に公表してはいけません。
遺言書の保管者または発見した相続人は、相続開始後早めに、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、遺言者・相続人全員の戸籍謄本と遺言書(コピーでも可)を提出し、検認の申請をします。
家庭裁判所より日時の通知があったら、遺言書の原本を持っていき、家庭裁判所で内容を確認します。これは、相続人全員に公表すると同時に、内容が以後、書き換えられることを防止するためです。なお、検認の目的は、遺言書の内容を相続人全員に公表することであり、遺言書の「有効」「無効」を判断するものではありません。
封印のある遺言書の場合
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人、または代理人が立会いをして開封しなければなりません。事前に開封してしまった場合は、罰金が科せられることがあるので注意が必要です。
「事前に開封してしまった」、「検認をしていない」からといって、遺言書が無効になることはありません。ただ、例えば、遺言書に従って不動産の名義を変更しようとする場合は、検認済の遺言書でなければ相続登記ができないなど、後で面倒なことになりかねません。
遺贈
遺言によって遺言者の財産の一部、または全部を与えることを「遺贈」といいます。
遺贈により財産を受け取る人を「受遺者」といいます。本来、相続人とならない第三者にも遺言で「遺贈」することができ、「受贈者」とすることができます。
遺贈には「包括遺贈」「特定遺贈」「負担付遺贈」「条件付遺贈」の4種類があります。
以下に、これらの特徴を記していきます。
包括遺贈
包括遺贈とは、相続財産を特定することなく割合で分ける遺贈です。例えば、「財産の1/3を長男に相続させる」など、一定の割合を特定の人に遺贈することです。
包括遺贈では、受遺者が本来は相続人にならない第三者でも、民法では「相続人と同一の権利義務を持つ」と規定しています。そのため、プラスの財産だけではなく、債務などのマイナスの財産も相続するため、注意が必要です。
また、遺贈の放棄をする場合には、相続人と同様に「相続開始の日から3ヶ月以内」に行う必要があります。
特定遺贈
特定遺贈とは、具体的に財産を指定して行う遺贈です。例えば、「株式は二男に相続させる」など、具体的に遺贈する物を指定した形式です。
遺贈を放棄する場合は、相続開始後、いつでも放棄することができます。放棄された財産は、他の相続財産と合わせて相続人が分割することになります。
負担付遺贈
負担付遺贈とは、一定の財産を与える代わりに負担も与える遺贈です。例えば、「家を遺贈する代わりに、住宅ローンを払うこと」などです。
ここでいう「負担」とは、必ずしも経済的なものとは限りません。例えば、「妻の介護をしてほしい」や「遺言者の墓を作ること」など、さまざまな負担の内容があります。
停止条件付遺贈
停止条件付遺贈とは、遺言書の条件が、遺言者の死亡後に成就されたときに効力が発生するものです。例えば、「孫が結婚をしたときは、土地を遺贈する」など、遺言の条件を満たさないと遺贈が発生しません。
なお、受遺者が遺言者の死亡前に条件を満たしたときは、無条件で遺贈されます。そのため受遺者は、相続が開始されると同時に、その目的物を受け継ぎます。このような場合には遺言者は、遺言を書き直していたほうが、死後の混乱を起こさせないことにもなります。
このように、遺言にはルールが決められているので、自身の遺族に対する想いを伝えるためにも、知っておいた方が良いでしょう。