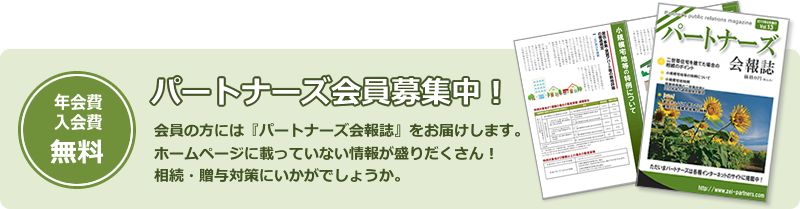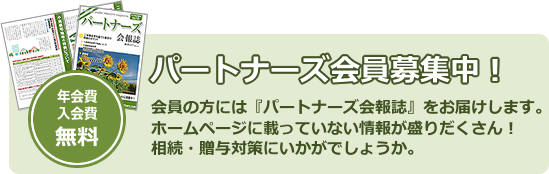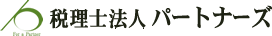遺言書がない場合の相続方法「法定相続分」とは?
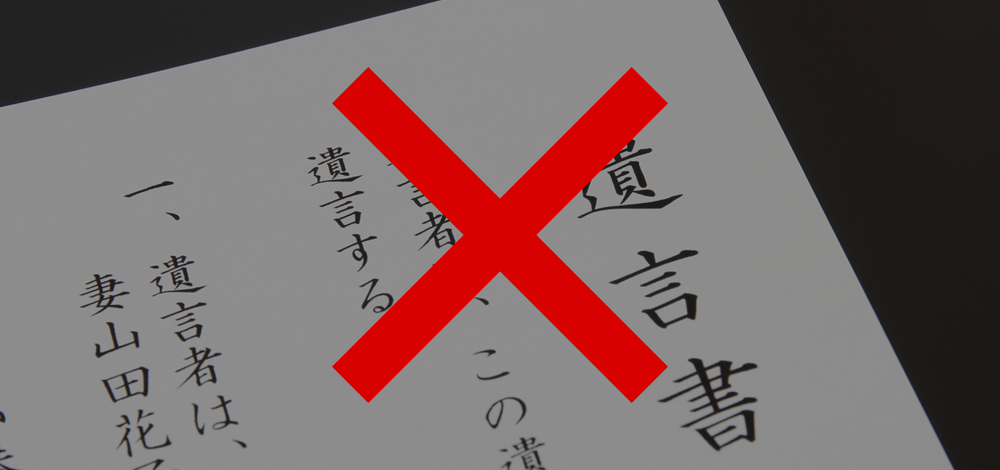
遺言書が無い場合、相続人の間で合意により財産を分割することになります。
民法では、同じ相続順位に相続人が複数いる場合には、目安となる相続の割合を各相続人ごとに決めています。これを「法定相続分」といいます。
法定相続分は相続する割合であり、「プラスの財産」だけではなく「マイナスの財産」も含まれます。
また、法定相続分は目安となる割合に過ぎないので、具体的に誰がどの財産を相続するかは相続人全員で遺産分割の協議をして決める必要があります。
協議がまとまるまでは預貯金も動かせませんし、財産の処分もできません。相続税の申告も完了できません。
目次
法定相続分の割合について
法定相続分とは、次の割合をいいます。
1)配偶者と子が相続人である場合
- 配偶者の相続分 1/2
- 子の相続分 1/2
2)配偶者と直系尊属(父、母、祖父母)が相続人である場合
- 配偶者の相続分 2/3
- 直系尊属の相続分 1/3
3)配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
- 配偶者の相続分 3/4
- 兄弟姉妹の相続分 1/4
上記1)2)3)の順番で優先順位が決まっており、「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」が複数いる場合には、上記のそれぞれの割合の中で均等に分けられます。
相続の割合に差を付けたい場合は遺言書が必要
法定相続分は平等が前提となっています。ただし、それぞれの家族の実情に照らして考えると、どうしても不公平感が出てしまう場合がございます。
例えば「親の介護を長年してきた人」「家業を継いで守ってきた人」「親の面倒を一切見てこなかった人」を、同じ相続分で分配しても良いのかということです。
ここで、
しかし、差をつけることによって相続人同士による問題が発生する恐れがあります。そのため、遺言によって事前に「誰に」「何を」引き継がせるのかを明確にして、問題を起こさせないようにする必要があります。
次のような場合は、特に注意が必要です。
相続人の仲が悪い場合
言うまでもなく、事前に決めておくことが得策です
財産の種類・量が多い場合
全財産を一覧にして、細かく相続人と相続分を明記しておくことが大事です。財産目録としても有効であり、相続人が財産を把握しやすいメリットもあります。
子供がいない夫婦
子供がいない場合、両親が既に亡くなっていると、財産は配偶者が3/4、兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合は甥姪)が1/4を相続することになります。
甥姪にまで財産が相続されることに抵抗がある場合は、「財産のすべてを妻○○に相続させる」と書いておけば、遺留分のない兄弟姉妹に財産がわたることはありません。
相続権のない扶養家族がいる場合
内縁の妻、亡くなった子の配偶者、事実上の養子などを生前扶養してきた場合、これらの人には相続権がありません。そのため、遺言を書かないで亡くなると、路頭に迷うことになりかねません。
再婚した夫婦の場合
子供からすると、義母に財産がわたることをよく思わない場合もあります。連れ子がいる場合なら、なおさらです。義母が亡くなったとき、お墓はどうするか、といったことも事前に決めておくことも大事です。
息子の嫁にも財産を分けてあげたい
長年、面倒をよくみてくれた息子の嫁にも、遺言で財産を残すことができます。
会社の経営者の場合
会社の株式や、その他の財産を複数の相続人で分割してしまうと、経営者としての力が分散されてしまいます。事業を引き継いだ後も会社の基盤が揺らいでしまわないように、遺言で事前に指定をしておいたほうが得策です。
負担付遺贈をしたい場合
年老いた妻や両親、障害のある子供、自分の死後に、面倒をみてもらう代わりに財産を遺贈するといった遺言をすることができます。
相続人がいない場合
子、兄弟姉妹、甥姪までも存在しない場合、最終的には国庫に帰属してしまいます。「生前お世話になった人に遺贈したい」「特定の団体へ寄付をしたい」という希望があれば、それを遺言書で残しておく必要があります。