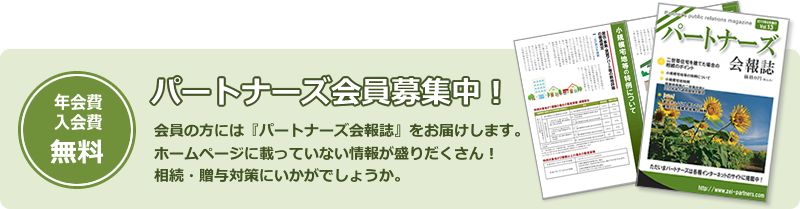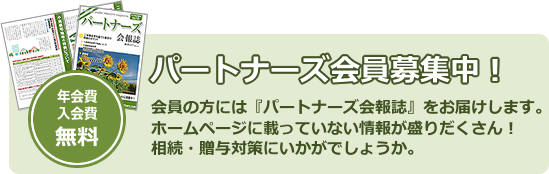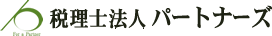遺言に納得できない場合の対処法
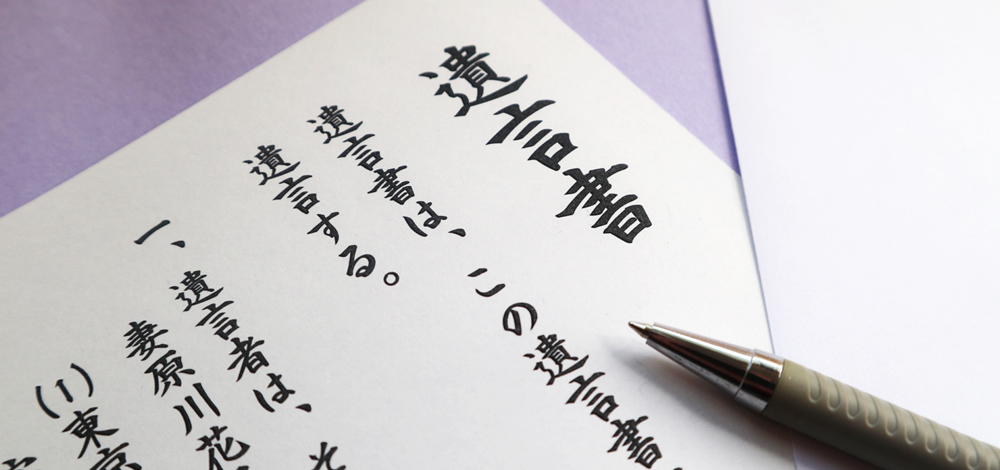
身近な家族であっても、限られた文章で気持ちや意図を伝えることは難しいものです。ましてや、みんなが納得できるような遺言書というのは、なかなか作れないものです。
また、相続人によっては、書かれている文章の解釈が分かれてしまうこともあります。
亡くなられた方の意思により作成された遺言書であっても、「自分の相続分があまりにも少ない」「自分の全く知らない人に遺贈する旨が書かれていた」「遺言書の内容どおりに分割されるか心配である」などの理由から、物申したい場合があると思います。
遺言書に納得がいかないと思っても、まずはもう一度落ち着いて読み返してみましょう。何か見落としがあるかも知れません。
それでも納得できない場合、その納得できない内容によって対処も異なってきます。
以下に、遺言書に納得できなかった場合の対処法を、5つのケースを例に説明いたします。
目次
case1. 自分の相続分が少ない場合
遺言書で指定された分割方法や相続分に納得がいかない場合、他の相続人とまず話し合いをしてみましょう。
他の相続人もこれに納得し、相続人全員が「遺産分割協議書」に同意して実印を押せば、それで分割は成立します。
遺産分割協議書とは
遺言がない場合は、法律に定められた相続人が遺産を相続します。相続人が複数の場合、遺産は全員の共同相続財産となります。
その共同で相続した相続財産を具体的に「誰にどのように分けるか」を、話し合うことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議には、相続人全員が参加します。そのため、相続人が全員揃わなければ、協議は無効になります。
協議が成立したら、その内容をまとめて書面にします。この書面が遺産分割協議書です。遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成し、全員の署名・押印をして各自1通ずつ保管します。
遺産分割協議書について、詳しくは以下のぺージもご欄ください。
遺産分割協議書とは?
作成のメリットや注意点は?
case2. 遺留分が侵害されている場合
本来、民法で定められている相続人が最低限もらうことができる相続分(遺留分)を満たしていないときは、期限内に遺留分減殺請求を行います。
相続人当事者での話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所を通じて調停を申立てることとなります。調停で決着がつかなければ、裁判となります。
case3. 遺言書に記載されていない財産が存在する場合
遺言書の内容に不満がある場合、それが被相続人の全ての財産かどうか、もう一度確認してみましょう。
遺言書に記載されていない財産が見つかった場合、その財産の分割は相続人で協議することになりますので、不満を解消できるかもしれません。
case4. 遺言書の形式に不備がある場合
遺言書の形式に不備がある場合は、法的には無効となるかもしれません。しかし、被相続人の遺志であることには変わりなく、その内容を尊重しながら相続人で協議し、遺産分割協議書を作成すれば分割は成立します。
ただし、その遺言書の内容について相続人の間では話し合いがつかないこともあります。そこで、遺言書自体の無効を主張するしか方法がない場合、家庭裁判所へ遺言無効の調停を申立てたり、遺言無効確認の訴訟を起こすことになります。
遺言の無効を主張するには?
遺言の無効を主張するには、何より証拠を集めることが重要です。検認※をした後であれば、まずは裁判所から遺言書のコピーを取り寄せます。
遺言書が、本人が書いたものかどうかわからない場合は、被相続人の筆跡がわかる手紙や手帳、日記を見つけ、筆跡鑑定をすることになります。
また、遺言者に意思能力があったかどうか疑わしい場合には、遺言書を作成した時の遺言者の状態がわかる資料(例:病院のカルテや介護記録など)を取り寄せます。遺言者の担当医にそのときの状況について意見をもらうのもひとつの方法です。
case5. 遺言どおりに処分が行われるか心配な場合
遺言書に書かれた相続分に不満はなくても、他の相続人が勝手に財産の処分をしてしまう不安がある場合、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てることができます。ちなみに遺言書でも遺言執行者を指定しておくことができます。
遺言執行者は、遺言者の死後、遺言に書かれた内容を実現させる人を指します。相続の財産目録を作成し相続人に交付することから、相続財産を管理し、名義変更等の必要な手続きまでを行ないます。
遺言執行者が選任された場合、他の相続人が遺産の処分を行ったとしても、その処分は無効となります。
遺言執行者は未成年者や破産者を除いて誰がなってもよいことになっており、相続人でもなることができます。
ただ、公平性を欠きトラブルとなりかねませんので、公平な立場の第三者がなるほうが良いでしょう。